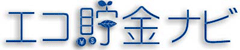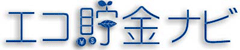�@��N���{���܂����u���Z�@�ւ̎Љ�I�ӔC�Ɋւ�����J�A���P�[�g�v�̍u�]���쐬�������܂����B
�Ȃ��A���J�A���P�[�g�{���y�щ��ʂɂ��܂��ẮA�ߋ���Web�y�[�W�����Q�Ɖ������B
�E���J�A���P�[�g�{��
�E���ʁi�ݖ₲�Ɓj
�E���ʁi���Z�@�ւ��Ɓj
���a���҂Ɍ����ā�
�@��X�a���ҁE�o���҂����m�ȃr�W�����������A���J�l�Ɉӎu���������邱�Ƃ��K�v�ł��B
�ǂ̂悤�ȎЉ��ڎw�������̂��A���̂��߂ɉ���I�����ׂ�������ɑO�����ɍl���ӎv�\�������邱�ƂŁA
�Љ�̎d�g�݂����ǂ����̂Ƃ��Ă������Ƃ��ł��܂��B
�@�a���E�����E�Z����ʂ��ċ��Z�@�ւƊւ��������Ƃ́A���̈ӎv�\���̑����ł��B
����̒�������эu�]�́A���̈ӎv�\��������ۂ̎肪����ƂȂ邱�Ƃ�ړI�ɍ쐬���܂����B
�������������ɂȂ������Z�@�ւɂ��ẮA���ڂ��������A���Ԃ������Ė�����`���Ȃ���T���Ă݂Ă��������B
�������āA�u�����玄�͂��̋��Z�@�ւɗa��������v�ƌ����Ă���������K���ł��B
�u�]�̍\��
�����L�̍��ږ����N���b�N����ƁA�Y������ݖ�̍u�]�̉ӏ��Ɉړ����܂��B
���_�P�DCSR�r�W����
���_�Q�D���ւ̎��g��
���_�R�D�n��o�ςւ̎��g��
���_�S�D�Љ�I���Ƃւ̎��g��
���_�T�D�����J�ւ̎��g��
CSR�ɑ���ۑ�ɂ���
- �s�s��s�͑��̋��Z�@�ւɔ�ׁA��������Ƃ���CSR�r�W�������쐬���A
CSR���|�[�g��Web�T�C�g�Ȃǂŏ�M���Ă���B
����͌��J����Ă���CSR�r�W�����Ǝ��ۂ̍s�����ǂꂭ�炢��v���Ă��邩�A
�߂Â��Ă��邩�@���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��邾�낤�B
- �n����s�A�M�p���ɂ͉c�ƒn��̔��W�ɍv�����Ă������Ƃ��r�W�����Ɍf���Ă���Ƃ��낪�����B
�����Ȃǂ̓s�s���Ƃ��̑��̒n���Ƃ̌o�ϓI�i���͊g�傷�钆�A
���̖����Ɋ��҂������������B
- �J�����ɂ́A���̋��Z�@�ւƂ͎�قȂ�A
�u�l�X����т������ċ����ł���Љ�̎����Ɋ�^����v�Ƃ����悤�ɁA
�u�n��̔��W�v�����u�ΘJ�҂̂��߂̔�c���E�����̕������Z�@�ցv�ł���_�������I�ł���B
- �g�}�g��s�A������s�A�����s�́A�{�Ƃ�CSR���ʂ������Ƃm�ɕ\�����Ă���A
��������̂悤�ȋ��Z�@�ւ������邱�Ƃ����҂����B
�܂��A�����X�^�[��s�͑��̋��Z�@�ւƂ͏������_���Ⴂ�A
�u���q���܂������̐S�z���������鎖������`�����鎖��
CSR���ʂ������Ɓv���ƍl���Ă���B
�E���Z�@�ւ̃r�W�����̗�
| �O��Z�F�t�B�i���V�����O���[�v |
�O��Z�F��s�ł́A�u�ō��̐M���v���l�����邽�߂ɂ́A
�u���q���܁v�u����E�s��v�u�Љ�E���v�u�]�ƈ��v��4�̃X�e�[�N�z���_�[�ɉ��l����A
���̌��ʂƂ��ĎЉ�S�̂̎����I�Ȕ��W�ɍv�����Ă������Ƃ��s���ł���A
���ꂪ�O��Z�F��s�́u�Љ�ɂ�����ӔC�v�A���Ȃ킿
�uCSR�iCorporate Social Responsibility�j�v�ł���ƍl���Ă��܂��B |
| �����s |
���s�́A�ߍ]���l�̌o�c�N�w�ł���u�O���悵�v�̐��_���p�������s��
�u�����ɂ��т����@�l�ɂ͐e�@�Љ�ɂ����v��CSR�̌��_�Ƃ��A
�u�n��Љ�E��E���E�n�����v�Ƃ́u�������h�v��Nj�����
�CSR���ͣ�̎����ɓw�߂Ă��܂��B
�Ƃ�킯�A�����厲�Ƃ���CSR�̒Nj����u��s�o�c�̗v���v�ƈʒu�Â��A
�o�c�Ɋ�����荞�ށu���o�c�v�ƁA���Z�Ɋ���g�ݍ��ށu�����Z�v�����H���Ă��܂��B |
| ���M�p���� |
�M�p���ɂ́A�u�l���ɂ���v�u�v�������ɂ���v�Ƃ������ݕ}���̐��_�����_�ł���A
���̒���ǂ����Ă������Ƃ����l����������ɂ���܂��B
�����ɂł́A���������M�p���ɂ̌��_�ɗ����Ԃ�A
�n��̕��X�����A�n��̔��W�ɕ�d����u�Љ�v����Ɓv�Ƃ��āA
�u������Ƃ̌��S�Ȉ琬���W�v�u�L���ȍ��������̎����v
�u�n��Љ�ɉh�ւ̕�d�v�Ƃ���3�̃r�W�����̎����Ɍ�����簐i���Ă��܂��B |
| �����J������ |
�������낤���́A�ΘJ�҂̂��߂̔�c���E�����̕������Z�@�ւƂ��āA
���Z�T�[�r�X��ʂ����Љ���^���ƂƂ��ɁA
�u�낤���O�v�̎����̂��߁A�����l�̕�炵�╟���̌���A
���S�ł���Љ�̑n����ڎw���A�Љ�v�������Ɏ��g��ł��܂��B |
�iA SEED JAPAN�����{�������Z�@�ււ̌��J�A���P�[�g���ʓ����쐬�j
�i�P�j���ɍv������a�����i�^�������i�ɂ�������g��
�v���̎�@�Ƃ��āA��t�E���Z���E�l�̊��z���s���̑��i�E���̑��A�Ƃ����S���ނ��������B
�P�j��t�Ɗ֘A�Â������g��
- ��t�z�Ɋւ��ẮA�P�N�x�̋��z���L�ڂ������Z�@�ցA
�v���L�ڂ������Z�@�ւ����݂��Ă���A����ł̔�r�͍�����A
�a���c���ɑ��Ĉ�芄������t����`�����Ƃ��Ă���Ƃ���́A
�L�ڂ��ꂽ����ł͗a���c����0.01���`0.03���Ƃ��Ă���Ƃ��낪�����B
����ŁA������s����́u��t���t����a���́A�a���W�߃c�[���̑��ʂ������A���q���܂̎u�������i�ɂȂ��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����v
�Ƃ����^��̐����������B
- �O��Z�F�t�B�i���V�����O���[�v�A���s��s�͐���t�@���h�ւ̓����z�ɉ�������t���s���Ă��鏤�i��
�����Ă��邪�A����ɂ��Z����̎��Ԃ͒��Ӑ[������K�v�����邾�낤�B
�Z����Ɋ��݂��Ȃ��Ƃ����_�Ɋւ��ẮA���z����t�ɏ[�Ă����a���Ȃǂ̋��Z���i�ɂ����Ă͂܂�B
- ���ɁA�t�@���h�̍w���z��A�f�r�b�g�J�[�h����уN���W�b�g�J�[�h�̗��p�z�ɉ�������t�Ȃǂ��s���Ă�����Z�@�ւ��������B
- ����A�����{��k�Ђ������ċ`�����Ƃ��Ċ�t�����鏤�i������������ꂽ�B
�Q�j���Z���Ɗ֘A�Â������g��
| ���炩�̂��Ƃ��s���Ă���i�܂��́A�s���Ă����j |
�s�s��s�i�݂��فA�O�HUFJ�A�O��Z�F�A�肻�ȁj
�n��i�����A�O�d�A����A���s�A�����A�����A�����X�A����j
�M���i�m���A���s�����j�A�J���i�����A�k���j |
| SRI�t�@���h�i����t�@���h�������j���������� |
�s��i�݂��فA�O�HUFJ�A�肻�ȁj
�n��i�����A�����X�j
�M���i�m���A���s�����j
�J���i�k���j |
| ����t�@���h���������� |
�s��i�O��Z�F�j
�n��i�O�d�A���s�A����j |
| ���z���^�̓Ǝ��̗Z�����x������ |
�n��i�����A����A�����j
�J���i�����j |
�iA SEED JAPAN�����{�������Z�@�ււ̌��J�������ʓ����쐬�j
- �a�����i�^�������i�ł͂Ȃ����A�����s�̊��i�t���E�������l���i�t���̎��g�݂́A����I�Ȃ��̂Ƃ�����B
����́A�Z����ɂ������������l���ւ̎��g�ݓx������Ǝ��̊�ŕ]�����A
����ɉ����ċ����D��������̂ł���B
- �e���Z�@�ւ̎�g�݂͐������Љ��Ă���A�ǂ�������[���B
����������́A�Z���X�L�[������тɂ��Ă̂��ڍׂȏ����J�Ɋ��҂���B
�R�j�l�̊��z���s���Ɗ֘A�Â������g��
| ���z���^���i�̍w���ɑ��A���[�����������a���̋�����D�� |
�n��i����A���s�A�����A�_�ސ�j
�M���i�����A�W�H�A���j
�J���i�k�C���A�l���A��B�j |
�iA SEED JAPAN�����{�������Z�@�ււ̌��J�������ʓ����쐬�j
- ���z���^���i�̍w���҂ɑ��A���[�������a���̋�����D�����鐧�x��
�l�̊��z���s���ɃC���Z���e�B�u��^����D��Ƃ�����B
���Ƃ��Ώ��M���́A�P�O���~�ȏ�̐ݔ��������s���������ɑ��Ē���a���̋�����D�����邱�ƂŁA
���z���^���i�w���̃C���Z���e�B�u��^���Ă���B
����a���̗D���̓��[����g�܂Ȃ��ڋq�����p�ł��A�����̍Œ���z���P�O���~�ƒႢ�̂ŁA
���[���̋����D���ȏ�ɕ��L���C���Z���e�B�u��^���邱�Ƃ��\���ƍl������B
�������A�u���z���^���i�v�ɃI�[���d���Z��������Ă�����Z�@�ւ�����ȂǁA
�ΏۂƂȂ鐻�i�̑I��ɂ͒��ӂ���K�v������B
- �����X�^�[��s�́A�uCO2�팸�ɍv������R���f�B�e�B�̎w�W�ɘA�����ċ��������肳������a���v
�������Ă����B��̓I�ɂ́A�Ζ��̑�փG�l���M�[�����ƂȂ�Ƃ����낱���⍻���A
�n�C�u���b�h�J�[�̃o�b�e���[�Ɏg�p�����j�b�P���⎩���Ԃ̎ԑ̌y�ʉ��ɍv������A���~�j�E���Ƃ������A
���i�̉��i�ɋ�����A����������̂ł���B
�u���������g�߂Ɋ����A�S�����߂�_�@�Ƃ��Ă������������v
�Əq�ׂ��Ă��邪���ꂪ���z���ɂȂ���̂��́A������v����B
�S�j���̑�
- �肻�ȋ�s�́u�⌾�M���ł̊�t�ɑ���萔���̗D���v�͋����[���d�g�݂ł���B
�i�Q�j���z���^�̓��Z���̎��g��
- �i�l�X�ȓƎ���j
�@���ɔz�������o�c���s����Ƃɑ��ᗘ�ŗZ�����s���Ȃǂ̎��g�݂��A�����̋��Z�@�ւɌ���ꂽ�B
���̏����͊e���Z�@�ւ��Ǝ��ɒ�߂Ă���A�����[���B
���Ƃ��A�g�}�g��s�́u���ɔz���������Ǝ҂ɑ��A
�@�b�n�Q�r�o�팸�A�A���}�l�W�����g�A�B�R���v���C�A���X�A�C����v�E�{�����e�B�A���A
�D���Ɗ����ɂ�������z���iCSR�j�v�̂T����14���ځv����]������Ƃ��Ă���B
���ɂ��A�O�d��s�́u��Ƃ̊��z���s����ʓI�ɃX�R�A�����O���A
�]�������N�����Z�������A����戵�萔���ɔ��f������v�Ƃ��Ă���B
- �i�Z�������j
�@����̉��ʂ���A�Z�������͈ȉ��̎O�_�\�\
�@��ʓI�f�[�^�A�A�����̔F�ؐ��x�A�B�����̂⍑�̐���A�Ɗ֘A���Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł���B
�@��ʓI�f�[�^�Ɋւ��āA�O�d��s�́A�u���o�c�̎����ɏڂ������č��@�l��ISO�R���@�֓��ɒ萫�]�����ϑ����A
��萸�x�̍����]�����s���B�v�Ƃ��Ă���A��ʁE�萫�̗����ʂ���̕]�����s���Ă���B
����ɁA������O���ϑ������邱�Ƃł�荂�x�Ȏ����ł̃T�|�[�g��ڎw���Ă���B
�@�F�ؐ��x�Ɋւ��ẮA���Ƃ����s��s�́u�@ISO14001�F�؎擾��ƁA
�AKES�i���s�E���}�l�W�����g�V�X�e���E�X�^���_�[�h�j�F�؊�ƁA
�B�u���s�{�Y�؍ޔF�ؐ��x�v�戵���Ƒ̔F���Ɓv����]�����Ă���B
�@�܂��A�����̂�M�p�ۏ؋���̗Z�����x���A���Z�@�ւ̗Z���p���ɉe�����Ă���ƍl������B
�����s�ł́A���쌧�������̕ۑS�Ɋւ�����Ɋ�Â��A���̎��ƔF��ɂ��Z�����鐧�x��݂��Ă���B
���Z�@�ւɖ{���K�v�ȃ��X�N�Ǘ��\�́i�u�ڗ����v�\�́j�Ȃ����Ƃ̂Ȃ��悤�ȁA
���悢�����̂����������o���Ă������Ƃ��K�v�ł���ƍl����B
- �i���тƓW�]�j
���тɊւ��Ă͋K�͂���e�����ꂼ��̋��Z�@�ւňقȂ邽�߁A��T�ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A
�����s���U�N�Ԃ�934���Ɠˏo���Ă���B
���܂�݂��Ȃ������A�Đ��\�G�l���M�[���Ƃ��������鑤�ւ̗Z�����A������҂���镪��ł���B
�l�X�ȃm�E�n�E�̒~�ς�l�ނ̈琬���s���Ăق����B�܂��A�����������i�t�Z���Ɋւ��ẮA
���ڍׂȕ]�����@�Ǝ��т��A�킩��₷���`�Ō��\���Ăق����B
�i�R�j���̑��̊��Ɋւ����g�݂ɂ���(���Ђ̓d�͍팸�A�ȃG�l�Ȃ�)
�@����̃A���P�[�g�ł́A���ЂɌ�������g�݂Ƃ��Ă͇@���z���^�X�܂ɔ��d���u�����A
�A�S�X�ɂ����ă��T�C�N���E�ߓd�B���R�ی슈���A�̎O�_�ɂ����ނˏW���B
�@�@�ɂ��Ă͑����̐M���E�J���Ŏ��g�܂�Ă���B�V�݁E���֓X�܂ł̑��z�����d�ݔ�������ȂǁA
���ۂɔ�p�������Ď��g��ł���_�͑f���炵���B
�@�A�ɂ��Ă͂قڂ��ׂĂ̋��Z�@�ւŖڕW���ݒ肳��Ă���B���̒��ł��O�HUFJ�t�B�i���V�����O���[�v��
CSR���|�[�g�ł́A�ڍׂȊ����׃f�[�^�����\����Ă���B
�@���Ƀ��j�[�N�Ȏ���Ƃ��āA�p�������̃��T�C�N���H������݂������s�����M��������B
�p���������Ђŏ�������ƂƂ��ɁA�]�菈���\�͂��g���Ēn����̔p�������̏��������������B
�@�܂��A���M���̂悤�ɖ��m�Ȉӎv�\���Ɋ�Â����g�݂Œ��ڂ��W�߂Ă�����Z�@�ւ�����B
���M���́A�u�����ɗ���Ȃ��v�Ƃ����p���������B���̉��ŏȃG�l���o�c�ۑ�Ƃ��ĔF�����A
�c�ƓX�Ɏ��Ɣ��d���u��LED�Ɩ������Ă���B
�܂��A����������u����ɎQ�����A��ʎs���ɍL���ӎv�\�������Ă���B
�b�n�Q�팸�A�ȃG�l��Ƃ����s���̏�ɖ��m�ȗ��O��ł��o�����_�͕]���ɒl����B
�i�S�j���Ɋւ�����g�ݑS�̂ɂ���
- �e���Z�@�ւ��A�����悤�Ɋ��i�t����[���ȂǁA�l�X�ȏ��i�J���Ɏ��g��ł���B
�����đ����̋��Z�@�ւ��A�������o�c�ۑ�A�܂��r�W�l�X�`�����X�Ƒ����Ă��邱�Ƃ��킩�����B
�������A�Z���̑����͊��������̏ȃG�l��ł�������A
���⎩���̂̐��x�̂��Ƃōs���Ă�����̂ł���B
�����\�ȎЉ�Ɍ����āA�K�v�ȃ��X�N���Ƃ�A���邢�̓��X�N��ጸ����w�͂��K�v�ł͂Ȃ����낤���B
���̂��߂̖ڗ����\�͌���ƐV���ȃX�L�[���̍\�z������ɓ����ׂ��ł���B
�i�P�j�n��ɑ���Z���̔䗦�i����Z���䗦�j
- ����Z���䗦������16�s���A����Z���䗦��80��������Z�@�ւ�13�s����A
��r�I�����䗦�ł���B����͉������Z�@�ւ��n����s�A�M�p���ɂ��唼���߂�̂ŁA
�g�D�̖����Ƃ��ē��R�̌��ʂƂ�������B
- �����s��44.8%�ƒ������Ⴍ�Ȃ��Ă���A�n����s�Ƃ��Ă͒������B
�i�Q�j�n��̌o�ϔ��W�ɍv�����铊�Z���̎�g��
- ���s��s�́A�n��̐����Y�Ƃɑ���x������������u�n�抈�����Z���v���O�����v
�Ŏ��т��c���Ă���B�i����22�N7���`23�N9�����܂ł̗v���s�z�c367���^628���~�j
�����āA�u���j�s�s�E���s�v�̑f���炵�����Ĕ������A�����ɂ킽���Ă܂����ĂĂ䂱���Ƃ���
��|�̃L�����y�[�������a57�N���s���Ă���B
- ���M�p���ɂ́A����23�N11���Ɂu�n�攭�W�x�����v���@�\���Ƃɕ������A
�n��̒�����Ƃɑ��Ă̎x�����������Ă��邱�Ƃ��f����B
���̓s�s��s�ł͖ڂ̍s���͂��Ȃ��n��̎��Ƃ�ϋɓI�Ɏx������̐����@�\�ʂɊg�[���A
�n��ɍ����������Z�@�ւƂ��Ă̓��F�����߂Ă���B
- �W�H�M�p���ɂ́u����o�c���k��v�́A������Ɛf�f�m�Ƃ̓��s�K��ɂ��
�o�c���k����P�w�����s�����̂ŁA�M�p���ɂ̃r�W�l�X�̂�������l�����Ŏ����I�ł���B
�܂��A�_�ˁA�W�H�u�����h�̑n�o��ڎw���A�u�_�˃Z���N�V�����v�ɖ��N���^���铙�A
�n��̓����������������M�^�̊����������ł���B
���̑����Z�@�ւ̒n��o�ςւ̎��g�݂̗�
| �����M�p���� |
- �u�n��Y�Ɖ������� �i���H��c���E���H��E��w���։��������j�v�悵�A������Ƃ��T�|�[�g
- ������Ƃ̉ۑ����������u���Ɣh�����Ɓv�A
��Ɠ��m�̃}�b�`���O���s���u�r�W�l�X�t�F�A�v�A
�H���i���������q���܂̓W����ł���u�������I���Y�E��i���{�s�v�������{
|
| �����s |
- ��ƌo�c�̎Q�l�ƂȂ�u��ƌo�c�Z�~�i�[�v��u�c�Ƌ������C�v�A�u�Ǘ��E�������C�v�Ȃǂ����{
- �V�����������X�X�̊������Ƃ��Čv�悳�ꂽ�����ۋT���s�X�n�J�����Ƃ̎����j�[�Y�ɑΉ�
|
| �P�H��s |
- �n��������w�Ƌ����Ō����J�����s����Ƃ�ΏۂɁA
�V���i�A�V�Z�p���ɑ��錤���J����V���Ƒn�o�A
�V����i�o��}�鎖�Ƃɑ��ď��������x�i��Ђ�����50���~����j��n��
|
�iA SEED JAPAN�����{�������Z�@�ււ̌��J�������ʓ����쐬�j
- ����܂Ŏ��g�ނ��Ƃ�����Ǝv���Ă����uNPO�����Z���v
�Ƃ����ʒu�Â��̋�̓I���x�������Z�@�ւ��A
���K�o���N����J���܂őS�Ă̎�ނɌ����A�܂����ъz�̌��J���i��ł��鎖�́A�a���҂Ƃ��Ă͊��}���ׂ��ω��ł���B
- ���̒��ł���������Z���̌`�Ƃ��Ă͊e�J�����s���Ă����˂��L���\����
�uNPO���ƃT�|�[�g���[���v�i�Ƃ��Ė�˂��L������e�J������сA
�O�HUFJ�t�B�i���V�����O���[�v�⋞�s�A�����M���̂悤�ȁu�����ݒ肵�Ă̗Z���v�Ȃǂ�����B
�܂��O�d��s�́u�Ȃ��Z���v��A�݂��فA�����A�����X�^�[��s�̂悤�ȓ���̒c�̂֗Z�����s���Ă����ۂ�����B
- �����A�g�}�g��s�̂悤�ȁu���x�͂Ȃ����j�[�Y�ɍ��킹�đΉ��v�Ȃǂ́A
����̐��x���E�����J�����҂������B
�܂����ъz�́A�Z����Ȃǂ������Ȃ����ɂ͒P���ɔ�r�͓�����A
���z�E���e����̓I�Ɍ��J���Ă�����Z�@�ւ����݂��A����ɂ��Ă��ϋɓI�Ȏ�g�݂����҂������B
�Љ�I���Ƃւ̎��g�݂̗�
| �ߋE�J������ |
�uNPO���ƃT�|�[�g���[���v�A��Q�Ҏs�������x���Z�����x�u��߂̂��ˁv�A
�u���傤�Ǝs������������g�Z�����x�v���̎��g�݂𐄐i |
| �O�d��s |
�u�݂�����NPO���[���v�𐄐i�B�n��NPO���������邽�߁A
NPO�@�l�����⎩���̂���ϑ����⏕��������ꍇ�ɁA
������t�܂ł́u�Ȃ������v�Ƃ��ĂP���ƍō�500���~�܂ŗZ���B |
| �݂��كt�B�i���V�����O���[�v |
�Љ�I�N�ƉƎx���Ő��E�I�Ȍ��Ђł���u�A�V���J�v�ƁA
���{�ł̊����x������юЉ�N�ƉƃT�|�[�g�ւ̋��͂ȂǂɊւ���
�uSTRATEGIC SUPPORT AGREEMENT�v������B�A�V���J�E�W���p���̊����x����ʂ��āA
�Љ�I�Ȗ��̉����Ƀr�W�l�X�̎�@��p���Ď��g�ގЉ�N�ƉƂ��x���B |
�iA SEED JAPAN�����{�������Z�@�ււ̌��J�������ʓ����쐬�j
- ���ׂĂ̋��Z�@�ւ��u�f�B�X�N���[�W���[���v�ƁuWeb�v��I�����Ă���B
���Ɂu�X���i�|�X�^�[�f���Ȃǁj�v�u�p���t���b�g�v�Ȃǂ���������Ă���B
- �f�B�X�N���[�W���[����CSR���������łȂ��A���Z�@�ւ̂��ׂĂ̊����ɂ킽��ڍׂȏ�L������Ă���A
��ʂ̗a���҂��Q�Ƃ���ɂ͐��I�����镔��������B
���CSR���|�[�g�́A��ʂ̗a���Ҍ����ɋ��Z�@�ւ̎Љ�I�Ȋ������Љ�Ă�����q�ł��邪�A
�n��A�M���A�J���ł͔��s����Ă��Ȃ��Ƃ��낪�����A���ʂƂ��Ă����Ȃ��Ȃ��Ă���B
- ����́A�R�X�g�ʂ�����L���Ǝv����v������ʂ��Ă̏�M�̏d�v�������܂��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
- �܂��A���Z�@�ւɂ���ď��}�̂��Ƃ̏��ʂ̈Ⴂ�������邽�߁A
���Z�@�ւ̏��ׂ����ꍇ�́A�v�����T�C�g���m�F���邱�Ƃ͂������A
�X���ɍs���Ăǂ̂悤�ȍ��q�����s����Ă��邩�m�F���邱�Ƃ��L���ł���B
- �Ƃ��đ����������Ă������̂́A�l����\�Z�̊m�ۂƂ������g�D�̐�
�i�����s�A�L��M���A�k���J���A�l���J���j��ACSR�����̔F�m�x����Ƃ������L��
�i�O�d��s�A������s�A�����s�A�k���J���j�ɂ��Ẳۑ�ł���B
- CSR�����ɑ���\���ȑ̐��������Ă��Ȃ����Z�@�ւ������A
�Г��O���킸�A�X�Ȃ�ӎ��̍��܂�ƃK�o�i���X���K�v�Ƃ���Ă���B
- �݂��كt�B�i���V�����O���[�v�A�O�HUFJ�t�B�i���V�����O���[�v�A
�ߋE�J�����ɂ���́A�u���Z�@�ւ̖{�Ƃ�ʂ��Ă�CSR�A�Љ�v���v
�Ƃ���������ꂽ�B�P�Ȃ�PR�����Ƃ��čs���Ă���CSR�������������A
�{�ƂƂȂ���Z������c�Ɗ����̒��ɂǂ�قǎЉ�Ƃ������_���܂܂�Ă��邩�Ƃ��������́A
�������a���҂ɂƂ��Ă����������������ł���B
- ���̑��A�O��Z�F�t�B�i���V�����E�O���[�v�͊��Z�p�̕]����@�A���Z�@�ւ̎x����@�ɂ��āA
�����J�����ɂ͏Ⴊ���҂ւ̑Ή��ɂ��ĉ��Ă���ȂǁA
����̓I�ȉۑ�������Ă�����Z�@�ւ�����ꂽ�B